|
近年、ポリフェノール効果等で注目されている「抹茶」。お菓子やサプリメント、様々な抹茶商品を至る所で見かけます。
注目を浴びている抹茶ですが、茶の湯で使われるものには濃茶と薄茶の二種類があります。
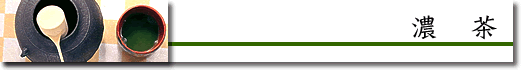
樹齢の古い木(樹齢が最低でも30年以上、主に70〜80年から100年以上の古木の若葉の芽先)から精製したもので、品質が優れ、刺激性は低いが味わい深いものです。
濃茶の分量を多く、湯を回数を分けて注ぎ、濃くたてるのが特徴です。一つの碗に客の人数分のお茶を一度にたてます。
薄茶のように泡をたてず、お茶とお湯を粒のないように混ぜ合わせ、茶筌の先でお茶をよく練り合わせて、緑色の美しい、艶のある、とろりとした液体に練り上げます。
茶入
主に陶製の小壷で、ふつうは象牙の蓋を付け、仕服と呼ばれる布地の袋を着せます。薬味入、香料入などに使われていた容器の転用品。
下記に形で分けた主なものを挙げてみました。
・肩衡(かたつき):肩が張っている形
・文琳:リンゴに似ている形
・茄子:ナスに似ている形
・芋の子:小芋に似ている形
象牙で作られた蓋の裏には金箔が張ってあります。これは、昔、象牙、金共に毒を消すものとして使用されていた為といわれています。
袋は、どんす、きんらん、間道、綿などの布地で作られており、上等の茶人になると複数持っています。

比較的若い木(樹齢が3年から15〜6年程の若木の新芽)から精製され、刺激性は強いが、味わいは軽く、濃茶よりやや苦味を持っています。
お茶の量に比べて、湯量を多く、よく混ぜながら空気を含ませ、細かな泡がこんもりと中高に盛り上がるようにたてます。
客一人に一服をたてます。
薄茶器
薄茶を入れる塗物器、一般的には漆器が多いです。主なものを下記に挙げてみました。
・棗(なつめ):利休型中なつめが基本で、平なつめ、小なつめ、大なつめ等がある
・金輪寺:ずん切りで、蓋の甲に丸みをもち、つた木地の上にすり漆、溜塗等がある
・中次:円筒形の中央に合い口があり、真塗(黒漆塗)が正式です。
・雪吹:中次の蓋と底とに面取りをしたもの
棗というのは、クロウメモドキ科の植物のナツメの実に形が似ている事に由来する名称です。
|
